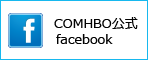「こころの元気+」2008年5月号より
自分の体の中にある治ろうとする力を信じて
多剤大量処方を適剤適量処方に切り替える7つのポイント
大下隆司/東京女子医科大学医学部精神医学教室
月崎時央/ジャーナリスト(取材・構成)
ポイント1
薬を出しすぎる多剤大量処方は、時代遅れの治療法です
日本では、抗精神病薬という精神科の病気の症状を抑える薬が、一人の患者さんに何種類も出されたり、そのさまざまな副作用を止める薬もたくさん出す傾向が、いまだに続いています。
これを多剤大量処方と呼びます。
先進国では、抗精神病薬と呼ばれる薬は、基本的に一種類、副作用止めも必要なときに限り最小限出すことが常識になっています。
日本の精神科医療も収容主義から、患者さんが地域のなかで元気に過ごすことを応援するように意識が変わってきています。
このために薬も、患者さんの症状を抑えつけることが目的ではなく、患者さんがよりよい生活をおくることを応援するような考え方で処方することが大切なのです。
そして患者さん自身が納得して服薬をすることが理想なのですが、現実には多剤大量処方が続いていることが大きな問題となっています。
ポイント2
薬は各々の症状を消し去るためではなく、脳全体のバランスを整えるものです
しかし、いまだに精神科では、一日に手のひらいっぱいもの薬をのんでいる患者さんが多くいます。
これは精神科医が、患者さんの症状や訴えに対して、それを治そうとさまざまな薬をどんどん追加してきた結果です。
多剤大量処方の場合、よく調べてみると、似たような効き目をもった抗精神病薬が一人の人に何種類も処方されていたり、極端な場合には下剤と下痢止めが同時に出されている、副作用止めの副作用止めが数種類も追加されているなどといった、誰が見てもおかしいと思える例もあります。
多剤大量処方が長く続いた場合、患者さんを困らせる症状が、本来の病気によるものなのか、薬の副作用なのかさえすでに見分けがつかなくなっています。
また長期間大量の薬に脳がさらされることで、本来の状態が変化してしまうこともあるのです。
こういった状態を断ち切り、適切な薬を適量服用するように変えていくことを薬のスイッチングとか減薬といいます。
ポイント3
チーム医療でみんなが目標を持てばスイッチングはきっと成功します
適剤を、適量服用する処方にしていくためには、もちろん精神科医の腕も必要ですが、患者さんの意識も大切です。
まず患者さんが、「なんとなく与えられた薬をのまされている」という気持ちをやめて、薬は自分の病気をコントロールするために自分の意思でのむのだ、という自立した気持ちが基本となります。
それにはまず、患者さん自身も、自分の服用している薬が、何という薬でどういった効果を持っているのかを把握する必要があります。
薬剤師さんに尋ねたり、本を調べたりしてもよいでしょう。
薬は、脳全体のバランスを整えるためにのむものです。
抗生物質のように、特定の細菌をやっつける効果があるわけではないので、一つの症状を治す効果が、薬剤一つに対応してあるわけではないことを知っておきましょう。
各薬の効果には重なる部分や、部分的に反対に作用するものも当然あります。
効能の重複をさけるためにも、自分の状態にあった薬を、まずトータルでバランスよく服用するという視点を患者さんも持ってほしいと思います。
ポイント4
鎮静のためではなく生活力を上げるのが薬の目的です
脳の働きにおけるバランスの悪さを改善するには、まず適剤・適量を守ることです。
脳のしくみは、完全に解明されているわけではありませんが、神経伝達物質ドパミンが関係していることは明らかです。
抗精神病薬は、このドパミンの量を調整する薬です。
ドパミンは、本来人間にとって情報を伝達するために必要な物質なのです。
でも精神の病気になった人の脳では、このドパミンが出すぎている部位と出ていない部位があるといわれています。
脳の場所によってアンバランスが生じているようです。
ドパミンが過剰に出ていると、外から入ってくる情報に過剰な意味をもって感じるようになってしまい、やがて幻覚や妄想があらわれるようになります。
でもこれを全部押さえつけるようなことを考えると、その人らしいいきいきした部分がなくなり無為自閉に陥ってしまうのです。
個人差もありますが、その人に応じてバランスの取れる量としては、70%程度ブロックするのがよいのだろうといわれ、それに必要な薬の量も明らかになっています。
残念なことですが、日本では、急性状態の混乱を鎮めるために、必要量の10倍もの量の薬を処方して鎮静させ、急性期が過ぎてもそのまま量を減らさないというケースも少なくありません。
本来、常に薬は引き算で考えることが必要なのです。
ポイント5
スイッチングには時間がかかるのがあたりまえ。
山あり谷ありをじっと我慢
スイッチングといっても、長い時間服用してきた薬をやめるのですから、そんなに簡単にできるわけではありません。
薬を減らすのに3年がかり、というのも珍しくはありません。
長い間の多剤大量服用によって、すでに脳の働き具合が薬の影響を受けて変わってしまっている可能性もあるからです。
減薬をすれば、多くの場合症状が揺れます。
症状が揺れたときにこれまで、強い薬で鎮静されてはっきりしていなかった幻聴などに気づくことがあります。
こうなると患者さんはもちろんですが、医者も怖くなって、減薬することをあきらめたり、さらに薬を追加してしまったりしがちです。
でも大切なのは、そこを少しこまめに観察してじっと信じて待つことです。
症状の揺れは、少し待っているだけで収まることが少なくありません。
ちょっと休憩して休んだり、一時的に鎮静させる薬でコントロールしながら、本当の長期的な目標をめざしてやっていく根気と勇気が必要なのです。
そこで大切なのは、看護師さんやソーシャルワーカーなどスタッフの理解です。
また家族や周囲の人々にも、減薬に対する知識を持ってもらうことが必要です。
みんなが同じ目標を持って、変化を見守る環境が大切なのです。
ポイント6
「眠れない!」の意味を、もう一度問い直してみませんか?
減薬を行っていくと、症状が不安定になり眠れなくなった、という訴えをする人が少なくありません。
しかしこういった訴えのなかに、睡眠薬を使った過鎮静状態の睡眠に慣れてしまって、普通の自然な眠りでは、寝た気がしないと感じるケースが少なからずあるようです。
本来、気を失ったように深く眠るということは不自然なことです。
また昼間に眠ってしまい、生活リズムが狂ってしまっていることもあります。
症状が安定してくるまでには、かなり時間がかかるものです。
眠りの質についても、考えてみてもよいかもしれません。
ポイント7
体に備わっている自己治癒力を助けることが薬の役割です
人間の体には、もともと自分の病気を治していく力があります。
これを私は自己治癒力と呼んでいます。
精神科の薬もちょうどいい量を使えば、本来の自分のもっている治ろうとする力を引き出すことができるのです。
特に、初めてのむ精神科の薬はシンプルな処方であるべきです。
適剤適量への切り替えの大切さはもちろんのこと、初めからシンプルな単剤を使えばその後の経過が違います。
10年先を見すえた処方を考えていきたいです。
精神科の病気を発症した人は、社会のストレスに弱い人たちです。
だからこそ、病歴の長い人でも自分らしい人生を取り戻すために適量の薬をのみ、適切なドパミンのシステムを取り戻すサポートが必要です。
患者さんの自己治癒力を信じ、それを引き出すために、薬の力を借りると考えましょう。
あくまでも主役は患者さんなのです。
「こころの元気+」2008年5月号より