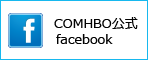「こころの元気+」2007年4月号より
患者さん自身が治療に積極的に参加し、責任を担うこととは
岩田仲生/藤田保健衛生大学医学部精神医学教室教授
コンプライアンスからアドヒアランスへ
ここ数年精神科臨床において患者さんが薬をしっかり服用することをさす言葉として「アドヒアランス」という語句が用いられるようになってきました。以前はコンプライアンスという語句がこのことをさしていたわけですが、これらの意味をもう少し掘り下げてみてみると、この言葉の変遷の背景にあることがたいへん重要だということがわかってきます。そもそもコンプライアンスの語感として「外からの決めごとや要求に従う・受け入れる・逸脱しない」というニュアンスがあり、医師の処方を受け入れて、決められた通り薬物を服用するというときに用いられてきました。アドヒアランスの方は「くっつく」とか「信奉する」という語感で主体的・積極的にその行為をしっかり行うというものです。こうしてみると「服用・服薬」という言葉も「服する」という語感からつくられており、コンプライアンス的語句かなと感じます。遵守という言葉も同様です。コンプライアンスは「服薬遵守」と訳されていますが、そうすると日本語でアドヒアランスの語感を正確に伝える言葉はあまり思いつきません。今までの精神科臨床でコンプライアンスという言葉が大きな顔をしていたのは単に言葉だけの問題でないことに精神科医として気づかされます。つまり日本語=日本の医療現場にはアドヒアランスという概念があまりなかったということを表しているのでしょう。
自己決定権とインフォームドコンセント
今まで医師の側からは、患者さんに決められたとおり薬をのんでもらうことは患者さんのためであり、当人が望む・望まないにあまり関係がないと考える習慣があったと思います。このことは少しむずかしい表現ですが、「医療要求の客観性」として医師が診療を行っていく上での一つの重要な理念でもあります。
医師は患者さんがある治療を受ける・受けないについて客観的な判断をしながら患者さんと対峙する習慣があります。
これは患者さんが「望む治療」をそのまますべて受け入れて行わないことの裏返しとして、「望まない治療」も説得して受けてもらうことがあるからです。
ここでは、またカタカナですがインフォームドコンセントという言葉が重要な役割をします。インフォームドコンセントは「知らされた上での同意」と訳されています。
「望む・望まない」に関して医師側は患者さんがどういう認識から「望む・望まない」を判断しているのかについて、専門家として可能な限り患者さんに理解できる形で説明をする必要性を強調しています。
つまり医師と患者がその問題に対して同じように理解・認識すれば引き出される結論についてはそんなに違いがないという信念があるからです。もちろんむずかしい事例については意見が相違することもあるかもしれません。ただし患者さんがその問題を深く正しく認識して出した結論であれば、医師はそれを尊重することには躊躇がないと思います。
「病識」をめぐって
さて精神科臨床においては、実はこの患者さんが自身の問題を正しく理解しているかが大きなポイントになります。
表に示したのは私が患者会・家族会などで薬にまつわる確認事項としてお渡ししているものです。その一番は診断についてです。これは病名の告知を受けているかということだけではなく、自分の病気をどのように理解しているのかを率直に先生と患者さんの間で話し合ってほしいという意味です。
━━━━━━━━━━━
表 薬にまつわる確認事項
━━━━━━━━━━━
●診断は?
●どの薬は一時的で、どの薬は長期間のむのか?
●「一時的」「長期間」とは具体的にどのくらいか?
●長期間のまないといけない理由は?
●今回の薬の量は何が根拠か?正しいのか?
●可能性のある副作用は?
●短期間なものと長期間のものと分けるとどうか?
●サポートする別の社会資源を利用すべきか?
この問題は医師の側からは「病識」という言葉で扱われます。精神疾患の場合症状として自分の病気についての認識がなかなか正しくもてないことがあります。精神科医の側も病識は大事だとはわかっていても、逆に症状を治めないと病識は出てこないという見方も一方であります。
まったく病識のない患者さんに本人の意志とは逆らって強制的に入院させ服薬を強いることも時にあるのが現実です。
精神科医の立場から言えば、その時はいやでもしばらく服用して症状が落ち着いてくると、患者さんも「あのときはつらかったけど今から思うと入院して薬をのんでよかった」ときっと後から思ってくれると考えるからできることだと思います。
しかしこれは急性期の治療においてであって、外来治療においては再度この点をよく検討しておくことがとても重要です。
一時的に調子が悪かったことは認めても、今は元気になったので病気は治った、あるいはそもそも病気ではなかったと考えたくなるものです。
ところが精神科医の方は一度診断名を告知すれば、それはそんなに簡単に治るものではなく、むしろ再発する危険性が非常に高い病気で、かなり長期間に渡って薬やカウンセリングといった治療を継続しなければならないと考えています。
ここにギャップがあると、そもそもよい医師―患者関係が築けなくなってしまいます。
先生は病気の専門家ですから、患者さんが病気について反論し批判しても、結局は言い負かされてしまいます。そのため、なかなか本音が言えなくなってしまうものです。
ではどうしたらよいのでしょうか?
病気や治療のことをよく知る
先生たちは何をもって患者さんたちに病気という診断を行っているのでしょう? そもそも「病気」とはなんでしょうか?
原因の医学的説明を求めても一〇〇年前と相変わらず精神科医は「不明」を繰り返しています。抑うつや不安はもちろんのこと、実は幻覚や妄想といった症状についても、程度の差はあれ元気で健康といわれている人にもおきています。
そうした症状の有無だけによる診断は結局うまくいきません。最終的にその人が普段通りの生活を続けていくのに困るか困らないか―障害があるかないか―で治療するかしないかの区分をしています。
ただし、ある診断名にくくられたとしてもその症状は人によってさまざまであり、昨今の研究成果によるとおそらくその原因も人それぞれさまざまなたくさんの原因が絡み合っておきているようです。
また治療についても、これまた確固とした医学的見地に基づいて考案された薬を使っているわけではないのです。
大まかにその薬を使った場合とそうでない場合を比べてある指標に関して使った場合がよいというものを薬として患者さんにすすめているのです。そうだとすると精神科医の方も「病識」と言いながら、正確な病気の定義ができないまま、また医学者であるにも関わらず科学的な作用機序が説明できない薬を用いて治療をしていることになります。
このような現状で、病気や薬のことが納得できないというのはある意味当然かも知れません。
しかしどの精神科医も患者さんが少しでも元気で幸せに過ごせることを心から願っていることは間違いなく、そうした先生との関係を大事にしていただき、自分の問題をどうしていったらよいか本音で語り合うことが大事ではないでしょうか。
そのなかで今わかっていること、どうして先生はその治療をすすめるのかをよく知り理解できれば、先生と患者さんの間でそんなに大きな意見の違いはおきないのではないかなと思います。
共同作業としての治療
あたりまえのことですが、治療を受けるのは患者さんです。薬という工場でつくられたモノを体の中にいれるのも患者さんです。
誰しもが健康で薬などのまなくてもよいに越したことはありません。また先生たちもそう願っていることに違いはないのです。
しかし色々な症状がなかなか治まらず普段仕事をしたり生活したりするのに支障が出てしまった場合には、サポートを積極的に受け入れていくことが、患者さん自身のみならず、患者さんのご家族やご友人にとっても大事なことです。
病気になる・ならないは一見個人的なことのように見えますが、実はそうではなく病気を社会全体の問題として受け止めて、共同作業として病気に立ち向かっていくことが人間のすばらしい面の一つであると私は考えます。病気になってしまうことそのものは不幸なことですが、それを一緒に乗り越える作業を共に進めることで、病気を抱えながらも幸せに暮らせるよう治療に取り組んでいくことが大事ではないでしょうか。