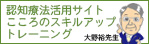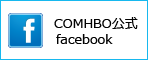特集2
親が思う「親なき後」のこと(216号)
○「こころの元気+」2025年2月号より
○申込について ○申込はこちら
○216号へ戻る
筆者:三良貴代美さん(大阪府)
筆者:赤池千明さん(静岡県)
信頼できる人を
筆者:三良貴代美さん(大阪府)
長女は小学低学年で精神症状を発症しました。
私は看護師で精神科に勤めたこともあり、状態が悪くなると入院、病状が改善すれば社会生活に復帰できると考えました。
ただ、症状が残っているのに入院するまで悪くない状態はどうなるのか?
◆伝えていること
私はたくさん勉強をした結果グループホームを運営することにしました。
グループホームには「親が突然倒れて入院した」「両親が施設に入った」など、急に1人になった方の相談があります。
そのとき本人は、初めての慣れない環境の慣れない人達の中で、生活を始めなければなりません。
私は今、関わる親御さん達に「親が元気なうちに子を託せる人を一緒に探すことが大切」と伝えています。
◆障害福祉サービス
障害福祉には相談支援事業というものがあり、福祉サービスの調整をしてくれます。
支援員は生活の計画を立ててくれるので全体を把握しやすいです。
また、訪問看護は定期的に訪問してくれるので日々の状態の変化がわかり、主治医と連携しているので薬の調整が必要な場合はスムーズに進められます。(家まできてくれるサービスについては→コチラ)
お金に関しては、社会福祉協議会で日常生活自立支援事業という金銭管理をお願いできる事業もあります。
たしかにどれも福祉サービスなので人に左右され、退職や人事異動などで、ずっと担当してくれるとは限りません。
中には頼りない、心ない担当者もいるかもしれません。
ただ、親が元気なうちに第三者と関係性を築いていく様子を見せてあげてほしい。
一緒に信頼できる人を探すことで、担当者が変わっても新たに関係を築く方法を学べるのではと思います。
◆支援者を見つけておくこと
「わが子の不安が強いから誰かと関係性を築くなんて無理」と親があきらめても、親なき後、子は1人では生きていけません。
1人暮らしをするならなおさら、トラブルが起きても1人で対応しなければなりません。
「助けて」を言える支援者を親が生きているうちにできるだけ多く見つけておくことが一番重要だと考えています。
今、私は娘と一緒に料理を始めました。
少しでも安心して未来に備えられるように今、できることをひとつずつ実践しています。
親なき後のお金
筆者:赤池千明さん(静岡県)
「親なき後のお金のやりくり」とは、「どんな収入があってどのように支出するか」ということだと思います。
ほとんどの当事者の場合、収入は障害年金と就労収入、支出は最低限度の生活に必要な経費と考えてよいでしょう。
しかし、これだと大部分の人は収入が不足します。
この点がお金についての親の心配と不安の核心なのです。
課題は「予想される収入不足の生活に備えて親はどんな準備をすべきか」です。
◆利用しやすい制度に
これにはさまざまな方法がありますが、私は現在の信託制度(しんたくせいど)を改革し、もっと利用しやすくならないだろうかと考えます。
親なき後の場合、信託制度は親が生存中に委託者(いたくしゃ)として自分の財産の管理と処分を受託者(じゅたくしゃ)と契約し、子である受益者(じゅえきしゃ)に契約による利益を与えるしくみをいいます(くわしくは⇨特集3へ)。
受託者には、信託会社や信託銀行等の営利組織がおもになります。
家族や弁護士、非営利組織等でも可能なのですが、現状では利用しにくいのが実際です。
利用しやすいように法改正が必要なのではないでしょうか?
さらに成年後見制度でも、信託の受託ができないのだろうか、とも考えます。
次に残す財産はどうでしょうか。
これには、預貯金や不動産、生命保険、相続時の遺贈分等が考えられます。
特に預貯金や不動産は相続時にきょうだい等とのトラブルがないように、公正証書(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)で親の意思を明確にすることも大切でしょう。
これらは一時金なので、信託等のしくみを利用して分割して本人に渡すとメリットがあります。
生命保険では、親の死亡時に受益者である本人に分割して支払う方法もできます(くわしくは⇨特集3へ)。
◆親にできること
とはいえ、現実はそんなに簡単ではありません。
頭の痛いことです。
つまり「親なき後」とは残された者の人生の問題なのです。
親には限界があります。
できることは、本人の生き方を信頼し、一回だけの人生をまっとうするように祈ることだけかもしれません。
○「こころの元気+」2025年2月号より
○申込について ○申込はこちら
○216号へ戻る