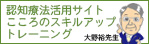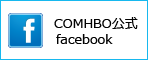特集1
ため息はなぜ出るのか?(213号)
○「こころの元気+」2024年11月号より
○申込について ○申込はこちら
○213号へ戻る
筆者:白石弘巳
埼玉県済生会 なでしこメンタルクリニック
▼生きるために必要!
「ため息」は、急に大きく息を吸いこみ、大きく息を吐き出す呼吸行動です。
「ため息」は動物にとって大切な役割をしています。
たとえば、「ため息」をつく遺伝子を欠損したネズミは、通常の呼吸はできるのに、やがて肺の病気で死んでしまうという実験結果があります。
「ため息」は呼吸器官を健全に保つ役割を担っていると考えられます。
また、「ため息」の前後で、心拍数や脳の覚醒レベルが変動するそうです。
乳幼児突然死症候群という病気では、「ため息」が心拍数や脳の覚醒レベルに必要な変動を生まないため急死が起こると考える研究者がいます。
くわしいメカニズムの解明は今後の課題ですが、「ため息」が生命の維持に大きな役割を果たしていることをうかがわせる例といえます。
▼「ため息」は感情がスイッチする際に生じる
古今東西「ため息」と感情は関連づけられてきました。
音楽家のJ.S.バッハ(1685-1750)は「私のため息、私の涙は、数えきれない。毎日憂いや悲嘆がなくならない」という曲を作り、
日本の古典『義経記』には「武蔵坊余りの嬉しさに腰を抑へ、空へ向ひてため息ついてぞ居たりける」という文が出ています。
これらの例から「ため息」は、苦しみ、落胆などのつらい感情だけではなく、安心や喜びなどのうれしい感情に伴っても発生することがわかります。
○どちらが先か?
ただ、「ため息」と感情の変化のどちらが先なのかは必ずしも明確ではありません。
感情と関係する扁桃体という脳の部分には、大きな呼吸のときだけ反応する入力経路があるそうです。
そのため「ため息」が感情に影響を与えているようにも思えますが、実感としては、感情によって「ため息」が出るようにも思います。
どちらが正しいかは、呼吸と感情に関わる視床下部や水道周囲灰白質などを含む脳内ネットワークの動きが解明されたときにわかると思います。
▼「ため息」が多いのは問題?
「ため息」が多い人について検討した論文を見つけました。
Sodyら(2008)は独自に設定した基準に照らして「ため息」の多い「ため息症候群」の40人を調べ、
①32.5%の人に発症に先立つ心的外傷体験があった
②25%は不安性障害と診断されていた
③3年間追跡したが、重い身体疾患の発症はなかった
などの結果を得ました。
彼らは「ため息」が多いからといって過剰な心配は不要と結論しています。
○症状か防御機能か?
だとしても「ため息」は心的外傷や不安など心の病と何らかの関係はあるようです。
その際、「ため息」は消去すべき症状なのか、問題を解消しようとする生体の防御機能なのかが問題となります。
結論は出ていませんが、作業中の「ため息」が覚醒度を上げ作業能率を高めるという実験結果があり、私は生体の防御機能のような気がしています。
▼「ため息」は人のいないところでつきましょう
これまでの結論として、「ため息」にはわからないことが多いけれど、過度に問題視する必要はないといえそうです。
もう一歩進めて、「ため息」が生体の防御機能の1つで不安の軽減などに役立つ可能性に着目して、「ため息」をつく健康法などは考えられるでしょうか?(⇨特集3へ)
この際「ため息」は、本来不随意的に生じる呼吸(意識せずにつくもの)なので、発生させる方法が課題となります。
意識して「ため息」をつくことは、ヨガやマインドフルネスなどで勧められている深呼吸と似た効果を生むのかもしれません。
ただその場合、「ため息」は近くにいる人の感情にも伝染すること、
特に意図的もしくは過度に「ため息」をつかれたと感じた人から「ふきハラ」(不機嫌ハラスメント)と受け止められる場合もあることを忘れないようにしたいものです(⇨特集6へ)。