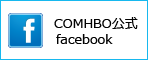こころの元気+ 2013年12月号特集より
特集3
怖れから希望へ─メンタルヘルス映画の動向
新宿フレンズ家族会
加藤玲
不安と怖れ
精神疾患は古くから文学作品や演劇の題材でした。
ヒッチコックが『サイコ』で震え上がらせ、『羊たちの沈黙』や『シャッターアイランド』は不気味さが際立ちます。
最近でも、『それでも、愛してる』のうつ病の主人公のショッキングな行為や、友人を吸血鬼と疑う美しい少女のゴシックホラー『モスダイアリー』、奇妙なできごとが主人公を襲う『テイク・シェルター』等は、事実か妄想か…と観る人を不安にさせます。
また、『サイド・エフェクト』は薬の副作用と犯罪を絡めた巧みなミステリー、『ラブ&ドラッグ』は製薬会社のすさまじい売りこみを絡めたおもしろいラブ・コメディですが、これらが精神疾患の状況の正しい理解につながるとは考えにくいのです。
実話の映画
一方、『ビューティフル・マインド』は、ノーベル賞受賞者のジョン・ナッシュの苦悩を、離婚した妻が愛情をこめて支える姿を描き、『路上のソリスト』は、壊れたヴァイオリンを弾くホームレスの天才音楽家ナサニエルに、取材した新聞社のコラムニストが医療、住居を与えコンサートまで企画。
しかし彼が願ったのは援助者ではなく、「友人」…ハッとします。
身体障害者と介護人の友情を描いた『最強のふたり』も、『人生、ここにあり!』や『むかしMattoの町があった』もいずれも実話です。
当事者の苦しみや願いを取材したからでしょうか。
対等な人間としての立場、障害者の人権や人生を選択する自由など、考えさせられます。
地域医療をめざす今、きびしいストレスフルな社会ではなく「ともに生きる」ために、もっとおだやかな社会をつくれないでしょうか。
『精神』は岡山の小さな診療所のドキュメンタリーで、障害者自身が語ります。
しかしそれはつらい過去…。診療所に安らぎはあっても、地域ではまだむずかしい日本の現状を感じます。
味わい深い作品
『明るい瞳』は、障害ゆえに家族や村人から邪魔者扱いされるフランスの少女が、ひとりで旅に出て、ドイツの森番の家に迷いこみ、森の光の中でのびやかに息づきます。
パリで入院していたホームレス女性が故郷のアイスランドへ送還され、主治医のフランス人女医が訪ねていく『陽のあたる場所から』では、精神科すらない小さな町で、おぼつかないなりに主婦の場を得て暮らす女性がいました。
理解し合える関係は、まず触れ合うことから。
『家の鍵』では、年間預け放しだったアスペルガーと身体障害の息子を、リハビリ施設に送り届ける父親の戸惑いや、重症の娘の養育にすべてを捧げた母親のさびしさが身にしみます。
弟が久しぶりに会う自閉症の兄『レインマン』は、ようやく心が通い合ったときのあたたかさが胸を打ちます。
躁うつ病の男性と心の傷ついた女性が出会いダンス大会に出場する『世界にひとつのプレイブック』は、ギャンブル依存の父親の息子への不器用な愛も味わい深いです。
1966年から2003年のイタリアの歴史を背景に、家族を描いた6時間の大作『輝ける青春』。
冒頭、兄弟は少女を精神病院から逃そうとして失敗します。
繊細な弟は、あえて規律と力の支配する軍隊や警察に入り、心がこわれていきます。
精神科医になった兄は少女と再開。精神病院を解放したフランコ・バザーリア医師の若き日が題材になっています。
障害者や家族の偏見を越える努力、それを取り巻く社会の変化、そして薬での回復が見こめる今、古い時代の作品と比較すると、病気ではなく人間に焦点をあて、共感や希望を兆した作品が増えたように思います。