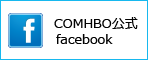「こころの元気+」2018年6月号(136号)より
いろいろ応用できる認知療法をじょうずに使ってみませんか
※連載「いろいろ応用できる認知療法をじょうずに使ってみませんか」→コチラ
大野裕(おおのゆたか):認知行動療法研修開発センター理事長
File.107 主役は自分自身
「アメリカで開発された認知行動療法が日本で本当に役に立つのか?」という質問を受けることがあります。
確かに自分の考えを主張して通そうとする傾向が強いアメリカ人と、自分の考えはおさえながら相手の気持ちを忖度することで、お互いの意思疎通をはかる日本人とは対話の仕方が違うように思えます。
そのようにコミュケーションの形が違う日本人に、アメリカ人に効果的な対話療法が役に立つのだろうかという疑問が出てくるのはもっともです。
認知行動療法の効果
そこで私達は、抗うつ薬を8週間のんでも症状が改善しなかった患者さん達に協力していただいて、認知行動療法の効果を調べてみました。
80人の患者さんのうち、40人はそのまま薬物療法を続け、40人には薬物療法に加えて16週間の認知行動療法を受けてもらったのです。
すると16週間後に症状がほぼ消えた人が、薬物療法だけだと20%だったのが、認知行動療法を受けた人達では42・5%になっていました。
確かに認知行動療法は日本の患者さんにも役に立ちそうです。
それだけではありません。研究が終わって1年後にもう一度状態をたずねると、症状がほぼ消えた人は、認知行動療法を受けていた人達では72・5%(薬物療法だけの人では42・5%)になっていました。
その間、認知行動療法を受けていなかったのですが、それでも7割の方の症状がほぼなくなっていました。
このことは認知行動療法が面接を通して症状を改善する効果があるだけでなく、面接の中で認知行動療法のスキルを身につけるとストレスに対処する心の力がつくことを示しています。
認知行動療法の本来の目的は、患者さんが自分で自分の治療者やカウンセラーになれるように手助けすることだといわれているのですが、まさにそのことを裏づける研究結果が得られたのです。
カウンセラーも医療者も
認知行動療法だけでなく、精神療法やカウンセリングというと、カウンセラーがいろいろとアドバイスをするものだとよく誤解されます。
最近『マンガでわかる心の不安・モヤモヤを解消する方法』(池田書店)という本を監修したのですが、そのマンガの最初の案では、カウンセラー役のスマートフォンアプリが主人公にアドバイスする場面がたくさん出てきました。しかし実際は、カウンセラーや医療者が具体的なアドバイスをすることはあまり多くないので修正してもらいました。
特に認知行動療法では、患者さんに対応策を考えてもらうことを大切にします。その意味で、カウンセラーや医療者は応援団でコーチなのです。
相談に来ている人の心に寄り添いながら、必要なときに役に立ちそうなヒントを伝えるのがその役目です。
そうすれば、患者さんが自分で考え、工夫をしていってもらえるようになります。
専門家と呼ばれる人から、いくら、「こうすればよい」と言われたとしても、心から納得できなければ身につきません。
認知行動療法の創始者のアーロン・ベック博士は、「肌で体験することが大事だ」と言っています。
悩んでいる本人がいろいろ工夫をしながら、「こうすればうまくいく」とか、「これはまずかった」と体験を通して気づきを広げることが、役に立つ工夫を考え出すために大事になります。その意味で、認知行動療法の主役は患者さん自身です。
患者さんが主役というのは認知行動療法に限らず薬物療法でも同じです。
薬の効果や副作用の出方は人によって違うため、薬をのんでどうだったかを患者さんにいろいろと教わりながら処方を調整することが大切です。
このように患者さん中心の治療を進めることで、患者さんは自分の人生を自分の足で歩いて行く力がついてきます。患者さんの人生の主役が患者さん自身であることを考えると、このことはとても大事です。
だからこそ、患者さん自身が主役として、治療に積極的に参加して、自分らしい人生を生きていっていただきたいと考えています。