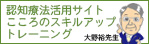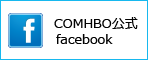コンボの動き
vol.138 コンボが主催・開催した活動や今後の開催予定です。
○「こころの元気+」2025年4月号より
○申込について ○申込はこちら
○218号へ戻る
○2025年2月15日開催 ※今後のこんぼ亭は→コチラ
第98回こんぼ亭 ※終了したこんぼ亭は→コチラ
ダメ!と止める支援から
ハーム・リダクション的な支援へ 報告
(関連雑誌→コチラ)
コンボ事務局より
2025年2月15日(土)は「ダメ!と止める支援から ハーム・リダクション的な支援へ」をオンラインで開催しました。
前半は、松本俊彦さん(国立精神・神経医療研究センター)に薬物対策の現状とハーム・リダクションについて話していただきました。
後半では、ライブで参加者の数多くの質問に答えていただきました。
▼Q&A(誌面以外のものも含め)いくつかご紹介)
●依存症やBPDの治療で信頼関係を構築するまでに、患者側は「この医者は信頼できるのか」と考え治療者側を試すような行動をとったり、診察時間を長めにとって欲しいと要求することもあるかと思います。
このような段階で、どのようなことに注意すればよいでしょうか?
●禁止事項や社会的に望ましくない行動を止めるのではなく、減らすという考え方が分かりやすいのですが、いざ対応する時にちゅうちょすることがあります。
具体的にリストカットやODの報告があった場合の心の持ちよう等を教えてください。
●看護師です。
リストカットやオーバードーズをくり返す10代の患者さんに、退院後の自宅ではどうしていただければよいでしょうか?
●SNS相談員です。
毎日のように、消えたい死にたいとメッセージがきます。
理由も答えてくれず、無力感しかないこともあります。
何か、今すぐ死ぬことから離れてくれるための効果的なメッセージがありましたら、教えてほしいです。
▼開催後アンケート(一部抜粋)
開催後に参加者からいただいたアンケートを(誌面以外のものも含め)いくつかご紹介します。
◆初めて参加させて頂きました。
質疑応答の時間が、約1時間、会の半分もあることに、驚きと感謝でした。
(たいがいの講演会、講座では、質疑応答は最後に2〜3件が多いので)(ゆうすけ)
◆松本先生が生きていて仕事をしてくれていてよかったなあと思いました。
そしてつながれた人たちが、全員とは言わずとも一人でもこの世の中にとどまってみようと思ってくれることで、その何倍もの周囲にいる人たちが傷つくことを防止していくのだろうと想像しました。
私にできることは、この社会の中でオーバードーズを含め、何かにすがって生きている人たちがいて、それは決して恥ずかしいことでも、悪いことでもなく、生きていくための精一杯のその人の努力なのだということを認めていくことなのではないかと思っています。
これから私と出会う人たちの中にも過去に依存の既往のある人や依存症である当事者の人がいると思います。
その時に私の「依存症」に対する姿勢・態度がその人たちを傷つけない、その周囲にいた人たちに「恥ずかしいことだ」と思わせないそんな自分でありたいと思いつつ、「べき」に縛られると自分も苦しくなるので、ほどほどに緩く生きられる世の中になってほしいと願います。(匿名)
◆ハーム・リダクションや規制をきびしくするからこそのリスク、より依存を強めてしまう状況について知ることができた。
「ダメ、絶対」を疑問に思ったことがないくらい、教育等の中で刷りこまれていることにも気づけた。
このままでいいのだろうかと支援者は不安になりがちであるけれど、つながり続けることの大切さや、モヤモヤをこちらが引き受けることができたのだと思えることは支援者にとっても救いになると感じた。(匿名)
◆中学生から下剤の乱用で1回100錠とかのんでいたので10代の女性の市販薬依存の現状に胸が痛みました。
ハーム・リダクションへの反発はいまだ根強いとのことですが、よいことが起こるのはゆっくりと決まっていますものね。
私もつながりをあきらめずに生きていきます。(ぴかりん)
◆学校関係者ですが、質疑応答で同じように思っている同志がいることを知り、希望になりました。(しゃけちゃん)
◆質疑応答が非常に充実していました。
著書もよいのですが、市来先生と(松本先生と)のコラボにより、講義以上に深みがある時間だったと思います。(匿名)
▼こんぼ亭亭主の市来真彦さん

▼松本俊彦さん