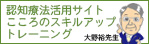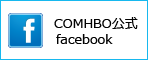ちょっと知りたい! ※連載について→コチラ
第121回
SST(218号)
○「こころの元気+」2025年4月号より
○申込について ○申込はこちら
○218号へ戻る
筆者:池淵恵美 (※「SSTで広がる人と人の輪」も参照)
神経科土田病院・ひだクリニックお台場
帝京大学名誉教授
▼SSTとは?
SSTは、social skills training の略称で、日本語では「社会生活スキルトレーニング」と呼ばれています。
認知行動療法の1種で、自分の気持ちを伝えたり、人とつながっていくためのコミュニケーションの練習をします。
ロールプレイ(役割を決めやりとりを練習すること)やモデリング(まずお手本を見せること)など、行動しながら学習するのが特徴です。
▼SSTとの出会い
私がSSTに出会ったのは、1986年に米国の学会でロバート・リバーマン先生の本を手にとったのが最初です。
帰国後、1988年のリバーマン先生の来日をきっかけに、丹羽先生や安西先生のご尽力で東大病院デイホスピタルでSSTが開始されているのを知り、私もお手伝いすることになりました。
それまでの診療スタイルと異なる認知行動療法であったため、皆で四苦八苦し、初めは四角四面に型どおりやることに力を入れたため、あんまり楽しくなく、参加する人達のノリもいまいちだったことを記憶しています。
ただ地域で生活していく上でまわりの人とつながることは大切で、SSTの可能性は感じていました。
▼SSTの広がり
今から30年前に「SST普及協会」が発足し、仲間がたくさん集まり、病院だけでなく、福祉領域の事業所や矯正・保護領域、学校領域などへと広がっていきました。
近頃は「誰でもSST」とのネーミングで、それこそ誰でも参加できるSSTが広がっています。
▼皆で一緒に
私はSSTの枠組みの中で、皆で一緒に「どうしたらよいか考えていく」創造的な時間が大好きです。
診察室の中でも、たとえば「1人暮らしがしたい」という相談を受けると、白板を持ちこんで、ご家族やほかの医療スタッフにも加わってもらい、一緒に1人暮らしのメリットやデメリットを考えていきます。
そんな中で、本人が結論を出して皆も納得ということになると、本当にうれしくなります。
それからロールプレイは、いわば未来を先取りして行動の練習をするわけなので、それで自信がついて前に進んでいくことができます。
もっと人とつながりたい人は、ぜひSSTに参加してみてください。