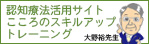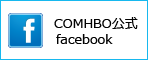新連載
どんなふうに伝えればいいんだろう?
SSTで広がる人と人の輪(218号)
○「こころの元気+」2025年4月号より
○申込について ○申込はこちら
○218号へ戻る
第1回 この連載について
筆者:池淵恵美
神経科土田病院・ひだクリニックお台場
帝京大学名誉教授
▼自己紹介
はじめまして。池淵恵美(いけぶちえみ)と申します。
精神科医です。
もう40年以上前からデイケアなどでリカバリー支援をやっていて、若い人が社会に巣立っていくのを楽しみに仕事してきました。
その中で認知行動療法の1つである社会生活スキルトレーニング(SST:エスエスティー)(⇨「ちょっと知りたい」参照)には時々お世話になっています。
友達がほしい、
まわりの人と気楽にしゃべりたい、
自分の気持ちを伝えたい、
距離をとりたい、
職場で上司にどう対応していいのか、
などなど「人間関係はむずかしい」と感じる人は大勢いると思います。
SSTでは、ロールプレイをしながら、よい点を伸ばして、皆に意見を聞いて、レパートリーを増やし、それぞれの人のなりたい自分をめざします。
▼ロールプレイ
役割を決めて、やりとりを練習する。例:右がさそう友人役で、左が断る役

▼日常生活で使えるスキルを紹介
デイケアンメンバーだけでなく、ご家族や学校の生徒や就職したい人、職場の人間関係に苦労している人など、SSTが役立つ人はたくさんいます。
そうした人達と一緒に「こんなときはどうすればいいの?」と悩みながら、気持ちを表現したり、相手との関係がよくなるように練習してきました。
私の頭の中にしまわれているたくさんのスキルを、ぜひ皆さんに使ってほしいので、この連載を始めました。
「これは使えそう」など、自分に合ったスキルを見つけて活用していただけたらと思います。
▼例・SSTで息子をサポート
あるデイケアでは月2回、土曜日に家族支援のグループをやっていますが、そこでもお母さん達が子どもにどう接したらよいか悩んでいるときなどに、SSTをやることがあります。
●島田さんの場合
島田さんは年配の女性で、30代の息子さんと2人暮らしです。
息子さんが大学1年のときに統合失調症になり、病状が重くてなかなか退院できず、島田さんはすごく心配していました。
デイケアに参加したときも、ぼんやりしてまわりと関われなかったのですが、根がまじめな努力家の息子さんは少しずつ回復して、障害者就労でお弁当工場に就職しました。
お総菜を流れ作業でお弁当に入れていく仕事でしたが、初めはきれいに盛りつけられず苦労していました。
それでも休まず仕事をこなし、職場の信頼を得て、就職して7年目にパートタイマーの主婦の人達のリーダー役をまかせられました。
●息子さんの困りごと
しばらくして家で息子さんの元気がないので、たずねてみると、「主婦の人達はみんな年上だし注意できなくて困っている」とのことでした。
そこでひらめいた島田さん!
そばの大きな観葉植物をパートさんに見立てて、まずお手本を見せて(モデリング)、それから同じように息子さんにやってもらいました。
▼モデリング
先にやってみて、お手本を見せること
●声のかけ方とポイント
「〇〇さん、ちょっといいですか? いつもお疲れ様です。初めはなかなかお総菜の量を同じにするのはむずかしいので皆さん苦労します。時々そばのはかりで重さをはかって、目分量がちょうどいいかどうか、確認してみてもらえませんか?」
にこやかに相手を見ながら、まずねぎらって相手の苦労を受け止めつつ、具体的なやり方を提案するのがポイントです。
息子さんは元気になって「これならやれそう」と言っていたそうです。
無事息子さんの仕事は続いていて、外来の帰りに時々デイケアに顔を出して元気な様子を見せてくれるので、デイケアのみんなは尊敬しています。
▼これから
この例は定型的なSSTではありませんが、家族会でコツをのみこんでいた島田さんが、じょうずに応用して息子さんのピンチを救いました。
これから何回か、SSTが役に立った例を読んでいただいて、皆さんに活用いただけたらと思います。
○「こころの元気+」2025年4月号より
○申込について ○申込はこちら
○218号へ戻る