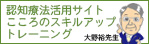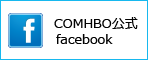特集3
医療機関でのODの対処(217号)
○「こころの元気+」2025年3月号より
○申込について ○申込はこちら
○217号へ戻る
筆者:上條吉人
埼玉医科大学医学部 臨床中毒学 教授
埼玉医科大学病院 臨床中毒センター センター長
▼ODの現状は?
救命救急センターに搬送される患者さんの10~15%は自殺企図、または自傷行為によります。
その手段のおよそ半分は、精神科処方薬、または市販薬のオーバードーズ(以下OD)です。
以前から、ベンゾジアゼピン(BZ)類などの精神科処方薬のOD患者さんは多かったのですが、
近年、とりわけコロナ禍以降は、10代から20代の若者を中心とした市販薬のOD患者さんが激増しています。

精神科処方薬や市販薬のOD患者さんは、さまざまな程度の意識障害で運ばれてくることが多いのですが、中には重症で、
空気の通り道がふさがりそう、
呼吸が弱い、
不整脈がある、
血圧が低い、
けいれん発作がある、
などのこともあります。
▼どんな処置をするのか?
精神科処方薬や市販薬のOD患者さんへの身体的な処置の4大原則は、
◆1「全身管理」
◆2「吸収の阻害」
◆3「排泄の促進」
◆4「解毒薬・拮抗薬」
です。

◆1:全身管理
なかでも「全身管理」が一番重要です。
たとえば
重度の意識障害で舌根(舌の奥の部分)が落ちて、今にも空気の通り道がふさがりそうな、いびきのような呼吸であれば、
気管にチューブを挿入して空気の通り道を確保します。
呼吸が弱ければ、
人工呼吸器でサポートします。
心室頻拍(しんしつひんみゃく)などの不整脈があれば、
電気的除細動を行う、また不整脈を止める薬を投与します。
血圧が低ければ、
急速に輸液する、または血圧を上げる薬を投与します。
けいれん発作があれば、
ジアゼパムやミダゾラムといった薬で止めます。
◆2:吸収の阻害(そがい)
「吸収の阻害」とは、ODした薬が消化管から吸収されるのを防ぐことです。
胃洗浄は、あまり有効ではないうえに合併症が多いので、今ではほとんど行われていません。
その代わりに活性炭を投与して、消化管の中に残っている薬を吸着させて、便と一緒に排泄させます。
◆3:排泄の促進
「排泄の促進」とは、すでに吸収されてしまった薬を効率よく排泄することです。
たとえば、血液透析法で血液の中の薬を取り除いてあげます。
◆4:解毒薬・拮抗薬(きっこうやく)
「解毒薬・拮抗薬」とはODした薬の毒性を弱めてあげる薬です。
◆心や環境も
ただしOD患者さんの場合は、身体的な処置だけでなく、精神科医、臨床心理士、精神保健福祉士などの先生方による「心のケア」や「環境調整」なども重要です。
▼予後はどうなのか?
精神科処方薬や市販薬のOD患者さんは、医学の進歩のおかげで、心臓が止まる前に救急医療施設に運ばれればほとんどの場合は救命されます。
仮に運ばれてから心臓が止まっても、
静脈・動脈体外式膜型人工肺(静脈・動脈エクモ)という機械で循環や呼吸をサポートしながら、薬が代謝されるまで待つ、
または積極的に血液透析法などで薬を排泄してあげればよいからです。
一方で、すでに心臓が止まってから発見されて運ばれてくるOD患者さんはほとんど救命することはできません。
精神科処方薬や市販薬のなかでは、命にかかわる不整脈が生じる三環系抗うつ薬やカフェイン、呼吸が止まってしまうバルビツール酸類などのODは非常に危険です。
OD患者さんを発見したら、なるべく早く119番通報することが重要です。
▼最後に
精神科処方薬や市販薬のOD患者さんにODの理由をたずねると、
「死にたかったから」など、自殺の手段としてODするケースが多い一方で、
「不快な気分を解消したかった」
「気分や意欲を上げたかった」
「気持ちをリセットしたかった」
「意識を飛ばして現実から逃げたかった」
など、生きづらさを脱して生き残る手段としてODしているケースも多いことがわかります。
ODされることの多いベンゾジアゼピン(BZ)類などの精神科処方薬や市販薬は死ぬ手段でもあり、生き残る手段でもあります。
こういった薬の存在を悪と決めつけられない葛藤を感じながら日々OD患者さんに対応しています。