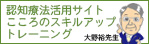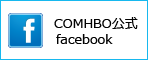ちょっと知りたい! ※連載について→コチラ
第119回
ニューロダイバーシティ(216号)
○「こころの元気+」2025年2月号より
○申込について ○申込はこちら
○216号へ戻る
筆者:井筒節(東京大学大学院准教授)
▼ニューロダイバーシティとは?
「ニューロダイバーシティ」とは、Neuro(脳・神経)とDiversity(多様性)を組み合わせた言葉です。
経済産業省のウェブサイト(※1)には、
「脳や神経、それに由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこうという考え方」とあります。
90年代頃から、特に「自閉スペクトラム症」「注意欠如・多動症」「学習障害」といった発達障害をめぐる違いを、能力の優劣ではなく、多様性と捉える流れの中で使用されてきました。
▼人は皆、違う存在
人はそもそも1人ひとり異なる存在です。
たとえば私は、東京出身の蟹座のB型ですが、47都道府県×12星座×4つの血液型の組み合わせだけでも、2256パターンあります。
実際には、ジェンダーや年齢をはじめとするさまざまな違いが多様性を彩り、その中には、脳・神経上の違いもあります。
脳には何百億もの神経細胞があるのですから当然です。
集中力を保つ、記憶する、行間を読む等、得意な人もそうでない人もいます。
同じ人の中でも時や状況によって異なることもあります。
たくさんの人との共同作業より1人で集中してデジタル作業をするのが得意な人も、オフィス業務より外で新しいお客さんと関わるのが得意な人もいます。
▼個性を尊重することで
こうした個性を尊重すると、個人・社会双方にとってよい結果が生じるかもしれません。
音や光に敏感な人、音声より文面のほうが理解しやすい人、たとえ話よりはっきりした表現のほうがよい人等、違いに配慮すれば、個人のウェルビーイングも社会のあり方も大きく変わっていくでしょう。
▼豊かな違いをカラフルな未来へ
すなわちニューロダイバーシティは、「マジョリティ(多数派)」を中心に考える社会から、脳・神経・認知などの多様性を認識し、違いに合わせて選択肢があるフレキシブルな社会環境に変え、誰一人取り残さずにウェルビーイングや生活の質の向上をめざそうというヴィジョンの表れです。
対話しつつ、社会の障壁をなくし、合理的配慮と共にオプションを建設的に増やしていくことで、豊かな違いをカラフルな未来につなげていきたいですね。